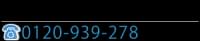後遺障害診断書書き直しは弁護士に頼まないと困難!?交通事故以外と何が違う?

「後遺障害の診断書を医師にお願いしようと思うけど書いてくれない場合があるって本当なの?」
「後遺障害の診断書の書き方なんて医師なら当然知っているんでしょう?」
「後遺障害の診断書の作成は弁護士に関与してもらった方がいいの?」
交通事故の被害者の方の中には、後遺症が残ってしまったため、後遺障害の診断書を医師にお願いしようと考えている方がいらっしゃるかと思います。
交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害の診断書と医師との関係について知らなくても当然かと思います。
しかし、後遺障害の診断書と医師との関係を理解しておかないと、後遺障害の十分な申請ができず、損をしてしまう可能性があるんです!
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の診断書と医師との関係
- 後遺障害の診断書を医師に依頼するポイント
- 後遺障害の診断書の作成に関し弁護士に関与してもらうメリット
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の等級が認定されるかどうかによって、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わることになります。
そして、後遺障害の診断書は医師に任せておけば、十分な内容のものを記載してくれると思われるかもしれません。
しかし、後遺障害の診断書をただ医師に依頼するだけでは適切な後遺障害等級が認定されず、適切な損害賠償額が受け取れないおそれがあります。
適切な後遺障害等級が認定され、適切な損害賠償額を受け取れるよう、後遺障害の診断書と医師との関係をしっかり理解しておきましょう。
目次
何となく、後遺障害の診断書は依頼さえすれば、医師がいつでも十分な内容のものを記載してくれるイメージをお持ちかもしれません。
しかし、実際のところは、そういったイメージとは違うようです・・・。
そこで、まずは、実際の後遺障害診断書と医師との関係を確認していきたいと思います。
後遺障害の診断書と医師との関係

後遺障害の診断書は医師だけが作成できる
交通事故のお怪我に対する手当てとしては、医師の治療以外にも、整骨院その他様々な方法が考えられます。
しかし、怪我に対する診断を行えるのは、医師免許を持つ医師だけとなります。
そのため、後遺障害の診断書は医師だけが作成できることになっています。
後遺障害診断書を医師が書いてくれないことも!?
書いてくれない理由は様々
しかし、実際のところ、後遺障害の診断書を医師が書いてくれないケースも存在します。
中には、こんなひどいことを言われてしまうケースもあるようです・・・
https://twitter.com/yositugu3/status/220401680150298624
上記の医師はどういった理由で書いてくれないのかはっきりしませんが、後遺障害の診断書を医師が書いてくれない理由は様々です。
その理由の中には、比較的正当な理由もあれば、そうでない理由もあります。
比較的正当な理由
後遺障害の診断書を医師が書いてくれない理由としてまだ治療の必要があることを挙げられる場合があります。
後遺障害診断書の作成時期は症状固定となった後になります。
症状固定とは
傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態
をいいます。
簡単に言うと治療を続けてもこれ以上良くならない状態のことです。
後遺障害とは将来においても回復が困難と見込まれる症状のことであり、上記の症状固定の時期の症状が、判断の対象となるからです。
医師が、まだ治療の必要があると判断している場合は症状固定の段階にはないといえるので、書いてくれない理由としては正当といえます。
もっとも、医学的な症状固定の時期と交通事故の賠償上の症状固定の時期が異なる場合もあります。
そのような場合には、医師に対し、医学的な症状固定の時期と交通事故の賠償上の症状固定の時期とが異なることを説明した上で、
後遺障害の診断書を書いてもらった後も治療には通うので、診断書を書いてくれないか
と説得してみることが対応策の一つとして考えられます。
また、初診時から長期間通院していなかった病院やはじめて受診した病院では、後遺障害の診断書を医師が書いてくれない理由として
治療の経過を診ていない
ことを挙げられる場合もあります。
後遺障害診断書は、治療をしたものの、残ってしまった症状や痛みを中心に記載するものです。
そのため、医師が後遺障害診断書を記載する場合、当初からの自覚症状や治療経過を把握していないと十分な記載ができません。
したがって、治療の経過を診ていないことは、後遺障害の診断書を書いてくれない理由としては比較的正当といえます。
このような場合、一定期間その病院に通院し、治療の経過を見てもらった上で改めて依頼してみることが対応策の一つとして考えられます。
| 症状固定前 | 症状固定後 | |
|---|---|---|
| 継続的に通院している病院 | ☓ | ○ |
| 継続的に通院していない病院 | ☓ | ☓ |
正当でない理由
ここからは、正当ではない理由を見ていきたいと思います。
まず、後遺障害の診断書を医師が書いてくれない理由として、病院として書かない方針であることが挙げられる場合があります。
この場合の対応策としては医師法第19条2項違反の可能性を主張することが考えられます。
診察若しくは検案をし(略)た医師は、診断書(略)の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
出典:医師法第19条2項
診察した医師は、正当事由がなければ、診断書の交付を拒否できないため、病院として書かない方針というのは正当な理由でない可能性が高いです。
病院として書かない方針というのは方便で、実際は別の理由であることも多いです。
そのため、後遺障害の診断書を医師が書いてくれない本当の理由を見極める必要があります。
また、後遺障害の診断書を医師が書いてくれない理由が、よくわからないから書けないであることが考えられます。
この場合の対応策としてはこちらからお願いしたい検査や記載方法を医師に伝えることが考えられます。
医師がよくわからないから書けないとはっきり言うことはまれであり、理由をよく見極める必要があります。
また、こちらからお願いしたい検査や記載方法を医師に伝える際、伝え方次第では医師が気分を害される可能性があるので注意しましょう。
| 理由 | 対応策 | |
|---|---|---|
| ① | 書かない方針 | 医師法第19条2項違反の可能性を主張 |
| ② | よくわからないから書けない | お願いしたい検査や記載方法を医師に伝える |
ご紹介したもの以外にも、想定される後遺障害の診断書を医師が書いてくれない理由はいくつか考えられます。
さらに知りたいという方は、以下のページにより詳細に記載されておりますので、ご覧になってみてください。
後遺障害診断書の書き方を医師は知らない!?
先ほど、後遺障害の診断書を医師が書いてくれない理由として、よくわからないから書けないことが考えられるとお伝えしました。
しかし、専門家である医師が診断書の書き方がよくわからないなんていうことがあるのか不思議に思われた方もいるかもしれません。
もっとも、医師は、交通事故の必要文書である後遺障害診断書の記載方法につき、特に医大などで教わるわけではありません。
また、医師は、治療をして怪我を治すのが仕事なので、治療の結果、残ってしまった症状には基本的にあまり興味を抱かない事が多いです。
そのため、後遺障害の診断書の書き方を医師がよく知らないという事態が発生することになります。
後遺障害診断書は医師しか書けないが、医師だからといって、十分な後遺障害診断書を書けるわけではないというのがポイントになります。
後遺障害診断書の作成を医師に依頼するポイント

後遺障害診断書の書き方を説明
ご覧のとおり、後遺障害診断書の書き方は医師がよく知らないことも多いため、作成を依頼する際、医師に書き方を説明する必要があります。
そこで、後遺障害診断書の書式に沿って各項目ごとに医師に依頼する際、説明すべきポイントを検討していきたいと思います。
①被害者の個人情報
まずは、書式の左上の部分に被害者の個人情報を記載することとなります。
具体的には以下のとおりになります。
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 職業
なお、職業欄は記載されないことも多いですが、そのことにより訂正を求められることはないようです。
②受傷日時
交通事故証明書記載の事故発生日を記載します。
事故の翌日以降にはじめて通院し、事故日を伝えていない場合、初診日を誤って記載されてしまう場合があるのが注意点です。
③症状固定日
先ほどご説明した、治療の効果が見込めず、あとは時間の経過による自然治癒を待つのみとなった状態に達した日を記載します。
先ほど岡野弁護士からご解説頂いたとおり、症状固定日は賠償や後遺障害の認定において重要な意味を持ちます。
にもかかわらず、被害者の方と主治医の方の症状固定日の認識が違う場合があるため、提出前によく確認する必要があるのが注意点です。
④当院入院期間
後遺障害診断書を記載してもらう病院での入院期間を記載します。
転院前に他の病院で入院していた場合、その入院期間は記載されませんが、 申請時に同時に提出する経過の診断書により確認できるので問題ありません。
⑤当院通院期間
後遺障害診断書を記載してもらう病院での通院期間を記載します。
転院前に他の病院で通院していた場合、その通院期間は記載されませんが、 申請時に同時に提出する経過の診断書により確認できるので問題ありません。
症状固定日後も通院することがありますが、通常通院の終期と症状固定日を一致させるのが注意点です。
また、実治療日数が記載されていない場合があるため、提出前によく確認する必要があるのも注意点です。
⑥傷病名
治療期間中の傷病名を記載します。
症状固定時に残存している傷病名だけが記載される場合もあります。
後者の場合には、後遺障害との関係で記載しておくべき傷病名に漏れがないか、提出前によく確認する必要があるのが注意点です。
⑦既存障害
後遺障害診断書に記載される障害を残す原因となった交通事故以前から被害者が有していた障害を記載します。
既存障害がある場合、交通事故と後遺障害との因果関係が争われることがあります。
そのため、既存障害があっても、今回問題となっている後遺障害とは無関係の場合は
- 無関係である旨を記載してもらう
- 既存障害の意味を説明した上で、記載してもらわないようにする
などの配慮が必要となるのが注意点です。
⑧自覚症状
症状固定時に被害者自身が感じており、医師に申告した症状を記載します。
特に重要なポイントになるので、後ほど詳しく説明いたします。
⑨各部位の後遺障害の内容
後遺障害の客観的証拠となる他覚症状と検査結果を記載します。
後遺障害診断書の中で最重要ともいえるポイントになります。
診断自体は、医師の判断であり、被害者が口出しをすることはできませんが
- 必要な検査
- 可動域制限の正確な測定方法
などを医師が把握していない場合もあるので、必要な検査や可動域制限の正確な測定方法を予め説明しておく必要があるのが注意点です。
⑩障害内容の増悪・緩解の見通し
後遺障害の症状の今後の見通しを記載します。
後遺障害とは将来においても回復が困難と見込まれる症状のことをいうため
緩解・軽減の見通しあり
などと記載されていしまうと、その記載を根拠に後遺障害認定が否定されてしまう可能性があるのが注意点です。
そのため、
- 「症状固定」
- 「今後の緩解の見通しなし(不明)」
などと記載してもらうのがポイントです。
お医者様の中には、時間の経過による自然治癒も含めて「緩解・軽減の見通しあり」と記載されてしまう方もいらっしゃいます。
その場合には、交通事故の賠償上は時間の経過による自然治癒があっても症状固定になることを説明する必要があります。
自覚症状を正確に伝える
後遺障害診断書の記載事項は医師の専権であり、基本的に被害者が口出しをすることはできません。
しかし、自覚症状は、ほぼ唯一被害者が書き方を指示できる部分のため、作成を依頼する際、自覚症状を正確に伝えるのがポイントです。
実際、後遺障害診断書の自覚症状の書き方次第で、後遺障害が認定されない可能性もあります。
具体的には、後遺障害の14級9号は「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」と規定されています。
そのため、例えば、常に痛みがあるが、寒いときや、天候不順のときに痛みが強くなる場合、自覚症状を
「寒くなると痛くなる」や「天候不順のときに痛くなる」
などと記載してしまいがちですが、そのように記載するとほとんど常時痛みがあると判断されずに、後遺障害が認定されない可能性があります。
その場合には、
「寒くなると痛みが増強する」や「天候不順のときに痛みが増強する」
などと、より正確に申告し、後遺障害診断書に記載してもらうのがポイントです。
後遺障害の判断は書面審査のため、同じ症状でも後遺障害診断書の書き方次第で結論が変わる可能性があります。
自覚症状をその場で主治医に正確かつ詳細に申告する自信のない方は予め書面に記載したものを主治医に手渡すというのも方法の一つです。
書き直しを医師に依頼する方法
先ほども記載したとおり、後遺障害診断書の記載事項は医師の専権であり、基本的に被害者が口出しをすることはできません。
そのため、後遺障害診断書の書き直しは医師が応じてくれないことも多いです。
そこで、後遺障害診断書の書き直しを医師に依頼する際には
- 医師の判断そのものに口出しをするわけではない
- 治療にとっては不要かもしれないが、後遺障害が残っていることを証明するためには必要な記載・検査がある
ことを丁寧に説明する必要があります。
書き直しを依頼するということは、医師の判断が間違っていると指摘していると捉えられかねないので、伝え方には十分注意する必要があります。
| ポイント | 理由 | |
|---|---|---|
| ① | 書き方を説明 | 医師は書き方を知らない |
| ② | 自覚症状を正確に伝える | ・唯一指示できる部分 ・書き方次第で非該当の可能性 |
| ③ | 書き直しの依頼は丁寧に | 判断が間違っていると捉えられるおそれ |
後遺障害診断書は弁護士に関与してもらうべき!?

弁護士が関与するとどう変わる?
ここまで、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際のポイントについてご紹介してきました。
もっとも、実際にご自身で医師に依頼するとなると中々難しいところもあると思います。
では、後遺障害診断書の作成について弁護士に関与してもらう場合、ご自身で依頼する場合とどう変わるのでしょうか?
作成要領を交付できる
ご自身で依頼する場合には、上手く依頼すべきポイントが伝えられず、結果的に医師に任せる形になってしまうことも少なくありません。
それに対し、弁護士が関与する場合、医師に対し後遺障害診断書の作成要領を提出し、適切に依頼すべきポイントが伝えられることが多いです。
追加検査・修正を依頼しやすい
ご自身で依頼する場合、追加すべき検査・修正点がわからず、主治医に対して追加検査・修正を依頼することが心理的に困難な場合も多いです。
対して弁護士が関与する場合、行うべき検査・修正点を適切に発見し、代理人として医師への追加検査・修正の依頼が容易なことも多いです。
認定の見込みが立てられる
ご自身で依頼した場合、受領した後遺障害診断書を確認しても、内容がよくわからず、後遺障害認定等級の見込みを立てられないことが多いです。
対して弁護士が関与した場合、後遺障害等級の認定見込みを事前に把握し、その後の賠償の見通しを立てられることも多いです。
| 関与あり | 関与なし | |
|---|---|---|
| 作成依頼 | 作成要領を交付 | 上手く依頼できず医師任せになることも |
| 追加検査・修正依頼 | ・行うべき検査・修正点を発見できる ・依頼が比較的容易 |
・行うべき検査・修正点を発見できない ・依頼が心理的に困難 |
| 認定見込み | 立てられる | 立てられない |
弁護士以外に関与してもらうなら
また、弁護士以外の後遺障害診断書の作成に関与してもらう方法もご紹介したいと思います!
後遺障害診断書分析サービス
調査してみたところ、京都の行政書士事務所が後遺障害診断書分析サービスを行っているようです。
こちらのサービスは、8,000円で、後遺障害診断書を分析し、分析結果を
「主治医に再確認なさった方がよいと思料される事項」
として書面を交付してくれるようです。
費用が低額であるというメリットがある反面、医師との書き直しの交渉やその後の賠償交渉はしてくれない等のデメリットもあります。
行政書士等のサポート
その他、行政書士等の専門家が後遺障害診断書の作成をサポートしてくれる場合もあるようです。
それぞれ、サービスの内容や費用は異なりますが、医師との書き直しの交渉までしてくれることもあるようです。
弁護士とそれ以外のメリットの差
このように、弁護士をはじめ、専門家に後遺障害診断書の作成に関与してもらうことにより、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
もっとも、弁護士に依頼した場合だけのメリットというのも存在します。
それは、後遺障害等級認定後の賠償交渉もしてもらうことができ、賠償額の大幅な増額が見込めるという点です。
ただし、事務所にもよりますが、費用が比較的高額になるのが弁護士に依頼する場合のデメリットといえます。
十分な内容の後遺障害診断書を手に入れたいのであれば、費用対効果も考慮した上で、上記のサービスの利用を検討してみるのが良いかと思います。
最後に、各方法のメリット・デメリットを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自分で行う | ・無料 | ・適切な判断できない可能性 |
| 後遺障害診断書分析サービス※ | ・低額 ・専門家の適切な判断 |
・医師との交渉はしてもらえない ・その後の賠償交渉はしてもらえない |
| 行政書士に依頼 | ・専門家の適切な判断 ・医師との交渉 |
・費用はまちまち ・その後の賠償交渉はしてもらえない |
| 弁護士に依頼 | ・専門家の適切な判断 ・医師との交渉 ・賠償交渉による増額 |
・費用が比較的高額 |
※上記で紹介したサービスを前提
適正な示談金の相場を自分で計算するなら

この記事を読んで、後遺障害が認定された場合、保険会社からいくら受け取れるのか気になった方も多いのではないでしょうか。
そのような場合、あなたが受け取るべき示談金・保険金の目安がわかる、こちらの計算機を使ってみてください。
氏名などの入力や面倒な会員登録等は一切不要です。
![]()
かんたん1分!慰謝料計算機
通院期間などを入れるだけでかんたんに慰謝料の相場がわかる人気サービス!あなたが保険会社から提示されている慰謝料は正しいですか?

入院期間や事故時の年齢など数項目を入れるだけ、1分かからず弁護士基準の示談金相場が計算できるので便利です。
後遺障害の診断書に関し弁護士に詳しく尋ねるなら

後遺障害の診断書に関し、もっと詳しく知りたいことや新たに生じた疑問が生じてきたときは、法律の専門家・弁護士に尋ねるのが一番です。
無料で質問できる弁護士、質問する方法も色々あるので、ご案内します。
お手元のスマホで無料相談するなら
気にかかることを今すぐ尋ねるなら、本記事を監修したアトム法律事務所のスマホで無料相談サービスがおすすめです。
こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。
電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。
仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。
保険会社や裁判所等との交渉ごとに強いので、示談金増額を希望される方には特におすすめです。
地元の弁護士に直接相談するなら
近くの弁護士に会って直接相談したい方には、こちらの全国弁護士検索をご利用ください。
当サイトでは、交通事故でお悩みの方に役立つ情報をお届けするため、
- ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
- ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている
弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。
頼りになる弁護士ばかりを紹介しているので、安心してお選びください。
何人かの弁護士と無料相談した上で、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもおすすめの利用法です。
最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の診断書と医師との関係や作成を依頼する際のポイントについてはお分かりいただけたのではないかと思います。
しかし、実際にご自身で医師に作成の依頼を適切に行うことは被害者ご自身では困難な場合も多いかと思います。
ご自身での医師への対応にご不安がある方は、まずは弁護士に相談だけでもしてみましょう。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。